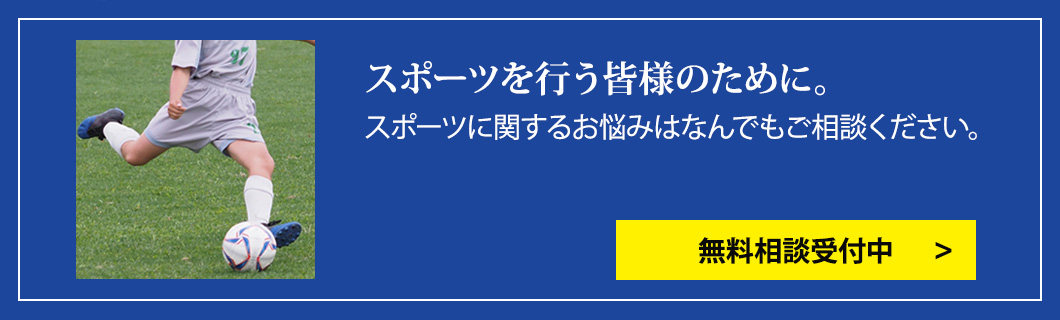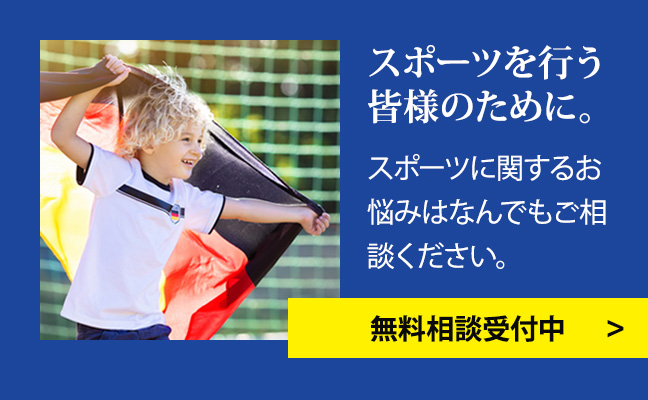スポーツとギャンブルの狭間 法律と倫理
はじめに
昨今、オンラインカジノに関わったとして芸能人が取り調べを受けたり、オンラインカジノ業者の広告に関わったアスリートに関する批判の声もあがっていますが、この問題、法律と倫理、双方から考える必要があるかと思います。
日本のギャンブル市場
前提となる日本におけるギャンブル市場ですが、公営ギャンブルやパチンコを中心に、巨大な産業として確立されています。2024年の売上は以下のとおりとのことです。
-
中央競馬: 3兆3134億円
-
競艇(ボートレース): 2兆5215億円
-
競輪: 1兆1892億円
-
地方競馬: 1兆1210億円
-
オートレース: 1091億円
また、パチンコ業界は15億円産業と言われています。totoが約1000億円です。
これだけでもとてつもない大きさの産業で、ギャンブル大国と言われてもしょうがない規模ですが、少なくとも売上は補足されていますし、何かあれば法律に基づく処罰の対象となる点でも一定の管理は及んでいます。パチンコを除くほかのギャンブル、スポーツ振興や地方財政の支援といった公共的な利益にも貢献しています。
太古の昔から行われているギャンブル自体を完全に防ぐことができない以上、ギャンブルが社会に与える負の側面を抑制しつつ、社会に利益を還元するにはこういった形にならざるを得ません。
海外オンラインカジノの課題と日本の法的対応の必要性
一方で、海外のオンラインカジノ、特にスポーツベッティングについては、日本国内で合法的に運営されているギャンブルとは異なり、法的な管理が不十分です。これらのサービスは日本の法律に基づく規制を回避して提供されているため、利用者の保護や公正な競技運営を脅かすリスクが存在します。
日本国内でこれを完全に防ぐことは現実的ではない以上、日本政府は適正な法的枠組みを整備し、ライセンス制度や監視機構を導入することで、スポーツ界や消費者を守る必要があります。どうせ闇で行われてしまうのであれば、合法化した方がいいという、よくみられる例です。
世界のスポーツベッティングでは、開始何分以内に何点入るかですとか、1人・2人の関与により結果が左右されうる事項も賭けの対象となってしまっています。すくなくともそういったものについて、賭けの対象から外す流れを作るべきです。
スポーツ界とギャンブル・八百長問題の深刻性
一方で、スポーツ界にとって、ギャンブルと密接に関わる八百長問題は最も忌避すべき問題の一つです。競技の公正性が失われれば、選手やファン、スポンサーの信頼は瞬時に崩壊し、そのスポーツ自体が衰退します。
日本でも既に相撲界においてそのような影響があったと思います。オートレースについて、我々世代では、モンキーターンという傑作漫画があってイメージはわるくないですが、数年前から元選手による八百長告白等により、人気が揺らいでいるように思います。
そのため、例えばオリンピックではRule 40という選手の商業活動を規制するルールがあり、そこではギャンブル関連の広告やプロモーションは禁止されています。
この規制は、スポーツの純粋性を守るための国際的な取り組みの一環です。日本国内でも、スポーツ組織やリーグが独自の規制を設け、選手や関係者がギャンブル業界と不適切な関わりを持つことを防止する必要があります。
スポーツ選手とギャンブル広告の関係性について
スポーツ選手がギャンブルに関連する広告に出演することについて、そんなに悪いことか、という意見もあるかとは思います。しかし、私たち弁護士は、一般の人に比べてギャンブルによって生活を破壊されている人の実態に接することがあります。みんな初めからギャンブルにはまろうと思って初めているわけではないと思います。
ギャンブル自体、一つの娯楽として素晴らしい面もありますので、少しでもいい形を模索していくのが必要だと思います。
プロ野球選手、元サッカー日本代表選手等の個人・法人の顧問、トラブル相談等を多数取り扱う
著作:「アスリートを活用したマーケティングの広がりとRule40の緩和」(東京2020オリンピック・パラリンピックを巡る法的課題(日本スポーツ法学会編)
・一般社団法人スポーツキャリアアドバイザーズ 代表理事
・トップランナー法律事務所 代表弁護士(東京弁護士会所属)
・日本サッカー登録仲介人
・日本プロ野球選手会公認選手代理人
・日本スポーツ法学会会員